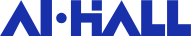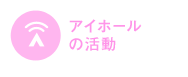アイホール・アーカイブス
平成29年度 次世代応援企画break a leg 参加団体インタビュー

今年度の「次世代応援企画break a leg」は、東名阪から三劇団に初登場いただきます。公演に先駆け、アマヤドリの広田淳一さん、無名劇団の島原夏海さんと中條岳青さん、劇団あおきりみかんの鹿目由紀さんに、劇団と作品についてお話いただきました。
■次世代応援企画break a legについて
岩崎正裕:本企画は今年で6年目になります。アイホールでは近年、中堅劇団に登場いただくことは多いのですが、新しい世代に使っていただく機会が、時代のせいか縮小傾向にあります。意図的に若手に門戸を開き、出会っていかないと、劇場の今後に繋がらないのではないかと考え、毎年5月~6月の時期にいくつかの日程を設け、全国的に公募し、そこから参加いただくみなさんに面白い成果をあげていただこうというのがこの企画の趣旨でございます。
今年は、初年度以来となる3団体が、東京・大阪・名古屋からお集まりいただくことになりました。まず、先陣を切っていただくアマヤドリさんは、東京を拠点に活動されています。先端で、スタイリッシュな方向性を貫いたなかで、演劇的成果をあげてらっしゃるのが印象的でした。無名劇団さんは大阪でも注目の集団です。作家の中條岳青さんの台本は非常に文学的成果が高く、僕自身「逸材だ」という感覚を持ちました。そこに演出の島原夏海さんが非常にくっきりとした演出をされています。そして、名古屋からは劇団あおきりみかんさんに登場いただきます。鹿目由紀さんは名古屋で長いキャリアをお持ちで、非常に大人数の登場人物を整理して出すところに演劇の妙があると私は思っております。こういった三劇団さんにアイホールに初登場いただきます。
■アマヤドリ『非常の階段』について
―劇団について

広田淳一(以下、広田):劇団が去年15周年を迎えたので、年に3作品を上演しました。その第1弾の『ロクな死にかた』という作品で、関西に初めて来ました。劇団を長く続けていて、公演回数も重ねているんですけど、我々の拠点が東京のため、今まで活動が東京だけになっていました。ただ、僕らの中で「東京のお客様=僕らのお客様」となっていることに、もっと危機感を持ったほうがいいとなりまして、数年前から北海道や福岡などでも公演を行い、去年やっと関西でも上演する機会を得ました。今回の『非常の階段』も、仙台、伊丹、豊橋、東京というツアーを行います。
僕たちの作品の特徴は、具体的な舞台美術を建てこまず、何もない空間や簡素な舞台装置のなかで、役者の身体性と会話のやりとりで舞台空間を立ち上げていくということです。俳優の身体の動きや、ダンスシーン、群舞などを使ってみせることも多いですが、フィジカルだけで言葉が無いというわけではなく、あくまで演劇ですので、物語はしっかりと台詞で会話劇としてつくり、かつ身体によって空間を立ち上げていくということをずっと追求しています。スタッフも含め、20名弱の劇団員がいるため、固定のメンバーで方法論や身体論を共有しつつ、ひとつの作品を練り上げていくというスタイルでやっています。
―『非常の階段』について
広田:この作品は、2014年に発表した「悪と自由の三部作」のひとつです。“自由とは何か”を考えたとき、我々は自由社会に生きているとか、自由のほうがいいよねとか、プラスのイメージばかりで語られることが多いですけど、“自由”の片側には“責任”が当然あるわけですし、人と人の“自由”がぶつかり合うところに“悪意”が生まれることもあります。“自由”と“悪”は表裏一体だと捉え、そのテーマで『ぬれぎぬ』『非常の階段』『悪い冗談』という三部作を発表しました。それぞれ「個人の悪」「社会の悪」「国家の悪」を扱っています。個人の悪を扱った『ぬれぎぬ』ではストーカー犯罪を、国家の悪を扱った『悪い冗談』では東京大空襲を題材に劇をつくりました。社会の悪を扱う『非常の階段』では、一時、巷を騒がせたオレオレ詐欺―最近は特殊詐欺という言い方をしますが―を取り上げ、その詐欺結社のメンバーたちが、ごく普通の平和な家庭に居候したことで、いろいろな問題や揉め事が起きたり、それぞれカルチャーショックを受けたりということを、物語の軸にして展開させています。

この作品のモチーフとして、台詞でも少し引用したのが、太宰治の『斜陽』です。社会を構成する最小単位が家族だと思うのですが、今、現代というこの時代は、長い時間をかけて作り上げられてきた従来の日本的な家制度や家族のかたちがだんだんと変わってきている過渡期にあるんじゃないかと感じています。旧来の家族のイメージ、いわゆる『サザエさん』的な家族の姿が、在りし日の夢のように語られてしまう時代、家族という社会のシステムが失われ始めている時代なのではないかと思っています。太宰治の『斜陽』は、戦後の混乱のなかで日本の華族が滅んでいく姿を描いた小説ですが、それを参考に、日本の“家族”が滅んでいくさまを劇のなかで描きました。ただ、滅んでいく側面だけを描くのではなく、今までとは違ったかたち、例えば友人といった血縁関係とは違う繋がりで“家族”をつくっていこうとする人たちの姿も、詐欺結社の人たちを通じて描いています。
詐欺は犯罪ですし、善と悪のどちらかと問われたら一般的に考えれば悪なわけですが、果たしてそれだけで終わらせて良いのかということもこの作品で問い直したいです。執筆にあたり取材をしたのですが、そのなかで感じたことがあります。それは、日本の格差、具体的にいうと教育の機会に恵まれなかった人たちが、大人になってどうやって社会でサバイブしていくかといったとき、多くの選択肢があるわけではないということ。そして、例えば親が子供を置いてどっかに遊びに行っちゃったとなったとき、昔は、祖父母が代わりに面倒をみたり手助けしたりという家族の厚みがあったけれど、今は核家族化が進んだことで、ネグレクトの問題と同じように、子供に被害が直接いってしまって餓死するみたいな痛ましい事件が起こる。昔のように、年長者にお見合いしなさいと言われるような、しがらみからは自由になったけど、その代償として、子供や力を持ちえない無力な世代に別のシワ寄せがいってしまっているのではないか。
もちろん、必ずしも皆がそういう不遇を背負っているわけではないですし、犯罪を擁護するつもりもないですが、もしかしたら、詐欺結社に入った人や、そうしたところに巻き込まれて抜け切れない人のなかには、人との繋がりが希薄で、自分を受け入れてくれるコミュニティがたまたま詐欺結社であって、そこに加わることで初めて自分の居場所を見つけたという人もいるのかもしれないと思いました。単なる愉快犯なのではなく、社会が抱えているもっと大きな問題の一端が、そうした犯罪として表出しているのではないかという気がしています。だから、詐欺をやっている人は悪いよねということだけではなく、自分たちが自由を謳歌できている分、誰かから何を奪ったんだろうということを、作品から問題提起できればいいなと思っております。
■無名劇団『無名稿 侵入者』について
―劇団について
島原夏海(以下、島原):私たちは、2002年に追手門学院中・高等学校演劇部の卒業生を中心に結成しました。2009年に精華小劇場で上演した『プラズマ』を最後に、約5年間、劇団活動を休止していました。実はその公演以降、それまで代表・作・演出を務めていた中條が、休団か退団かというぐらい、連絡が取れなくなりまして…。
中條岳青(以下、中條):はい、すみません。後ほどお話しします。

島原:(笑)。私の母が劇団制作をやっていて、高校演劇部の顧問だったのですが、休止後に残ったのは母と数人だけだったんです。それで私の個人的な思いもあり、もう一度復活させたいと母に申し出て、2014年にほぼ新メンバーで再始動しました。休団前は男性が多かったんですけど、再開時は20代半ばの女性が中心となりました。それで1年ぐらい経ってから中條が戻ってきまして(笑)。それ以降は中條が脚本を担当し、近代文学を翻案する「無名稿シリーズ」と、劇団員による集団創作で20代の女性のリアルな日常を描くシリーズと、2つの軸をベースに活動しています。両方とも私が演出しています。
作品の特徴としては、休団前は会話劇が中心でしたが、再始動後は女子が多かったのと、たまたま体が動く人がいたので、それならと、幻想的な群舞を積極的に取り入れています。実は中條の戯曲は、初見だとちょっと意味がわからない表現や言葉が多いんです。それをどう舞台に乗せるかを考えた結果、幻想的で日常的ではないテイストが多くなりました。また、陶芸や書道や華道や曼荼羅といった他の芸術とコラボレーションをした演劇をつくるという独自の取組みも行っています。
今回上演する「無名稿シリーズ」は、第1作目の『無名稿 あまがさ』が、2015年に應典院舞台芸術祭「space×drama」の優秀劇団に選出いただいたことをきっかけに、それ以降、シアトリカル應典院で上演してきました。今回、初めて、他の劇場でこのシリーズを上演します。実は『無名稿 あまがさ』はアイホールで上演したくて、以前、break a legに応募したんですけど、そのときは落ちまして(笑)。でも私たちは、受かるまでは出し続けるというスタンスなので応募しつづけて、それで今回、このような機会をいただけることになりました。
―『無名稿 侵入者』について

中條:まず最初に、私は大阪の中学校で教員をしておりまして、不在の5年間は教職に勤しんでおりました。
「無名稿」は、近代の日本文学を翻案し、現代演劇の視点から再構築して舞台化する作品群のことです。僕が久しぶりに劇団に舞い戻ってきて新作を書くとなったとき、せっかくなので巨匠に胸を借り、文学を舞台化したいと思ったのがきっかけです。やってみると意外と面白く、それ以降シリーズ化しています。“無名”には、「無名劇団」の無名と、多くの読者とその一人でもある私たちの解釈が入っているということを暗に意味しています。なぜ近代文学なのかといいますと、中学教員として若い世代と接していると、文学離れが大きな問題だと感じたからです。図書室で中学生と触れ合うと、生徒たちが手に取る本の棚が限られているんですよね。すごくポップなものや刺激的な現代小説、ライトノベルに興味関心が強くて…。それで、古典や近代文学も面白いということを、どうやって若い世代に伝えるかを考えたとき、新たな楽しみ方として、演劇という手法が合うんじゃないかと思いました。文学の普遍的な価値を、現代的な視線で再構築することで、新しい価値が生まれるのではないかと思い、始めたのがこの「無名稿シリーズ」です。
2015年に初めて川端康成の『あまがさ』という、A4で1ページに収まるような掌編を80分程度の演劇にしました。第2作目は2016年に横光利一の『機械』をモチーフに、そして、この5月に、大正時代の作家・倉田百三の『出家とその弟子』という、本来、舞台化を想定していないレーゼドラマというジャンルの戯曲を原作とした作品をシアトリカル應典院で上演し、第4作目として6月にbreak a legで梅崎春生の『侵入者』を取り上げます。

島原:『出家とその弟子』が5月、『侵入者』が6月と、約3週間で「無名稿」の新作を連続上演するというハードスケジュールに挑戦します(笑)。
中條:梅崎春生は、第一次戦後派とよばれ『桜島』や『幻化』という作品が有名で、戦時中に坊津の特攻隊基地で海軍に所属しており、第二次世界大戦を直接的に体験した作家のひとりです。ですが、作品を読むと、彼が自分の戦争体験をどのように捉えているのかがあまり見えてこない。基地で働く自分について描いた作品はあるのですが、特攻隊時代に何があってどう感じたとか、基地でどういう経験をしてどう思ったとかが一切語られていない。どこか第三者的に、斜め上から俯瞰していて、まるで他人事のように冷めた視点で自分を客観視しているんです。その感覚が今の私たちに通じるところがあると感じました。
僕は、私たちの社会や歴史の流れは、常に発展して新しいものに変わっているのではなく、文化や考え方や価値観はループしていると感じています。個人的には、今は新たな「戦前」を迎えているのではないかと…。だからこそ、今、この作品を読み解いていく意味があると思っています。
また、僕たちのような女性演出家と男性作家の組み合わせは、関西でも稀有な例だとよく言われています。彼女は僕の脚本を「読みにくい」とよく言いますが、僕は、戯曲は文学だと思っていて、ト書きやセリフ一つ一つに対して思い入れを持って書いているし、そこにはそれなりの強度があると信じています。彼女も演出として、身体性や声・コトバに対する強度をもって表現したいと思っている。その二つのぶつかりあいが、僕たちの劇団の面白みだと思っています。
特に、近代文学に取り組むにあたり、挑戦を恐れないようにしたい。文学は文字で残りますが、演劇は生の芸術で、表現した先から消えてしまう刹那的なものです。その二つの出会いがどういう化学変化を起こすか楽しみですし、僕たちは消えていくことを恐れずに演劇で表現していきたいです。「break a leg」という名前も、挑戦に対して恐れるなというメッセージだと感じていますので、脚本と演出がしのぎを削りながら生み出す新たな演劇作品をご覧いただければと思っています。
■あおきりみかん『つぐない』について
―劇団について

鹿目由紀(以下、鹿目):劇団あおきりみかんは、大学のOB・OG中心で旗揚げした劇団です。「あおきりみかん」は、青いうちに切ったみかんのことです。私がすっぱいものがすごく好きという理由だけでこの名前をつけました。当初は一回限りの記念公演で終わるつもりだったので、軽い気持ちで名前をつけたら、こんなに長く続いてしまってびっくりです。そのあと、劇団として継続していくにあたり、「すっぱい未熟なみかんが熟していく」と後付けをしました。あとで他の方に「ん」で終わる劇団は長続きしていると言われました。「少年王者舘」とか「青年団」とか「燐光群」とか。今年で19年目、公演数も今回で37回目とかなり回数を重ねています。
旗揚げ当初は一つの場所で展開するワンシチュエーション・コメディをやっていたのですが、「劇王」という劇作家協会東海支部が主催している短編演劇コンクールへの参加を機に、思い切って作風を変えました。このコンクールでは、劇作家個人として出場をし、三人以内の登場人物で20分以内の作品を発表します。それで参加するにあたり劇団内で大きな会議を持ち、劇団員に「ここで自分がやりたいことをやりたい」と伝えました。それまでの作風でもお客様から「次も楽しみに待っています」という声をたくさんいただいていたのですが、私のなかでだんだんマンネリ化したり、まわりに迎合しすぎているのではないかという疑いがふくらんでいて。それで一度、自分のやりたいことを思い切りやりたいと思い上演したところ、2007年の「劇王Ⅴ」で優勝しました。それをきっかけに、もう少し「実験的」なものに、そして「コメディ」から「喜劇」という言い方に変えて上演を続けています。笑えるけど内面では何かがうごめいているとか、表面上は喜劇的だけど実は悲劇的というようなことを表現していきたいと思っています。
劇団の特徴としては、毎公演、何かにチャレンジしようと努力をしているということでしょうか。チャレンジは他の皆さんもされていると思いますが、私たちのチャレンジは、肉体的負荷として具体的にどう実践していくかということです。例えば、前回公演の『ルート67』では誰かが常に舞台上で走り続けると決めて、本番中は休まずにずっと走り続けるとか、別の公演ではずっとつま先立ちでやるとか、ジャグリングを一カ月で覚えて本番でやるとか。泣きながら毎日ジャグリングを練習する人もいました。人によって得手不得手はありますが、劇団なので、何かひとつでもチャレンジして、その成果を劇にのせていきたいという気持ちがすごくあります。だから劇団員は今回はどんな無茶ぶりがくるかと怯えています(笑)。もちろん私も一緒にやるので、作・演出と俳優がお互いに必死にそのチャレンジをやっている、そんなさまも作品のなかで喜劇的にうつるようにできればと思っています。
―『つぐない』について

鹿目:今回も喜劇です。ただ、ずっと作品を作り続けていると、次に何か新しいことをやりたい、脱皮したいという気持ちになるのが常日頃でして。「劇王Ⅴ」から10年近く経つんですが、10年一区切りといいますか、今、私のなかで、モゾモゾした何かが芽生えてきています。もちろん今までのスタンスを大きく変えるつもりはありません。でも、何かいつもと違うことをやってみたいという思いもあります。新作なので、今の自分がいちばん感じていることを舞台にのせたいと思っており、そのなかで最近、気になっている「罪悪感」を描くことにしました。日常は罪悪感で成り立っていると思っています。それもちょっとした罪悪感。例えば、遅刻をしちゃったとか、台本が遅いとか(笑)、人の彼氏を好きになったとか。そこには罪悪が存在していて、その罪悪の解消の仕方で日常が動いている、そういうことが実は往々にしてあると思っています。前回の『ルート67』は、プロテクターをつけてずっと走っていて、少年ジャンプのように「努力・友情・勝利」に振り切った話だったんですけど、今回は内面的なことを女性の主人公に乗せて書いてみたい。そこから自分なりの喜劇が生み出せないかと思っています。もちろん俳優には、走り続けるような負荷ではないですが、もう少しじっとりした、内面的なものが肉体的なものに繋がっていくような負荷はかけていきたいと思っています。
今回、あおきりみかんは久々の関西公演です。私が福島県の会津若松市出身なので、地元で公演をしたいという思いが強く、近年は福島や仙台など東北での公演を重ねてきました。けれど、関西ではあまりやったことがなくて…。特にアイホールには、大学生のころ、仲間と車に乗りあわせて名古屋から芝居をよく観に行っていました。ぜひともやりたかった憧れの劇場です。今、自分が感じている最新のものをアイホールに持ってきたいと思っています。
(2017年4月、大阪市内にて)
■アマヤドリ ツアー2017『非常の階段』 公演詳細
■無名劇団 第26回公演『無名稿 侵入者』 公演詳細
■劇団あおきりみかん 其の参拾七『つぐない』 詳細間もなく!